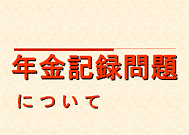2008年03月17日
後期高齢者医療制度 歳の離れた(年下の)妻はやや負担増
国民健康保険の被保険者が75歳になって被保険者資格を喪失し後期高齢者医療制度に加入することになる。
そうすると75歳未満の扶養されている妻は被扶養者ではなくなるため新たに国民健康保険に加入しなければな
らない。「後期高齢者医療制度における職場の健康保険の被扶養者だった人」の対象者は、
①制度施行日の前日(平成20年3月31日)に、職場の健康保険などの被扶養者だった人
②制度施行後に75歳になって資格を得た日の前日に職場の健康保険などの被扶養者だった人
のどちらかの要件を満たす人のことなので、「均等割額」の
・平成20年4月~9月までの無料
・平成20年10月から翌年3月までの9割軽減
・被保険者となった日の属する月から2年間の5割軽減
措置にはあてはまらず
夫が75歳で妻が仮に55歳とすると20年間 妻一人で国民健康保険に加入し 所得が無くとも国保保険料
(静岡市の場合) 均等割額 28,800円
平等割額 24,600円
介護分均等割 13,500円
合計 66,900円 が課されてしまう。
この所得の無い妻が75歳になって後期高齢者医療制度に加入すると
(静岡県の場合) 均等割額 36,000円
夫は年金生活者で所得が少ない、もしくはすでになくなっている可能性もあるので
均等割額の7割軽減が適用されると均等割額のみで 10,800円となる。
いまのところ健保や共済の被扶養者の優遇(軽減)は発表されているが国保の被保険者の場合一人になっても
(夫が後期高齢者医療制度の加入者になってしまうため)たとえ20年間あろうと75歳になるまで(自分が75歳に
なって後期高齢者医療制度の加入員となると最適基準の10,800円で済むことがわかっていても)66,900円という
6倍以上の国民健康保険料が課されてしまうのは何か特例の救済はあるのだろうか。
そうすると75歳未満の扶養されている妻は被扶養者ではなくなるため新たに国民健康保険に加入しなければな
らない。「後期高齢者医療制度における職場の健康保険の被扶養者だった人」の対象者は、
①制度施行日の前日(平成20年3月31日)に、職場の健康保険などの被扶養者だった人
②制度施行後に75歳になって資格を得た日の前日に職場の健康保険などの被扶養者だった人
のどちらかの要件を満たす人のことなので、「均等割額」の
・平成20年4月~9月までの無料
・平成20年10月から翌年3月までの9割軽減
・被保険者となった日の属する月から2年間の5割軽減
措置にはあてはまらず
夫が75歳で妻が仮に55歳とすると20年間 妻一人で国民健康保険に加入し 所得が無くとも国保保険料
(静岡市の場合) 均等割額 28,800円
平等割額 24,600円
介護分均等割 13,500円
合計 66,900円 が課されてしまう。
この所得の無い妻が75歳になって後期高齢者医療制度に加入すると
(静岡県の場合) 均等割額 36,000円
夫は年金生活者で所得が少ない、もしくはすでになくなっている可能性もあるので
均等割額の7割軽減が適用されると均等割額のみで 10,800円となる。
いまのところ健保や共済の被扶養者の優遇(軽減)は発表されているが国保の被保険者の場合一人になっても
(夫が後期高齢者医療制度の加入者になってしまうため)たとえ20年間あろうと75歳になるまで(自分が75歳に
なって後期高齢者医療制度の加入員となると最適基準の10,800円で済むことがわかっていても)66,900円という
6倍以上の国民健康保険料が課されてしまうのは何か特例の救済はあるのだろうか。