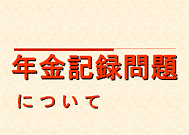2008年03月16日
後期高齢者医療制度 低(中)所得者層には、保険料負担軽減か。
社会保険や労務管理のセミナーを受講すると今年の制度改革として必ず話題にでるのが「労働契約法」とともに
「後期高齢者医療制度」がある。後期高齢者医療制度では、保険料は被保険者全員が納めることになる。
被保険者とは75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の一人一人のことだ。
保険料は(静岡県の場合)次のように決定される。
均等割額(36000円)+所得割額((総所得金額等-330,000円)×所得割率(6.84%)) =一人当たりの保険料
上記の式にあてはめると年金収入だけの被保険者については、収入額が153万以下の場合所得割はかされない。
収入が年金だけで夫婦二人の年金収入がそれぞれ153万以下だった場合は所得割は無く、均等割額の36,000円のみ
×夫婦二人分ということになるが所得が低い人は2割から7割の均等割額の軽減がありなおかつ職場の健康保険などの
被扶養者だった人の場合平成20年4月から9月は全額免除10月から翌年の3月までは9割均等割額の軽減があるため
国民健康保険料と比べてみると老人世帯の低所得(中所得)は負担が軽減されるとおもわれる。
国民健康保険(静岡市の場合)の所得割が無く夫婦二人の場合の保険料
医療分 均等割額 28,800×被保険者数=57,600円
平等割額 1世帯あたり 24,600円
介護分 均等割額 13,500×被保険者数=27,000円
合計 57,600+24,600+27,000=99,200円
となり、低所得者層で息子世帯といっしょにに暮らしていない場合は、いままで最低基準として納付していた額
10万前後とくらべ半分以下になる場合がごく一般的にでてくる。反対に年金収入が多いとか、普通に収入がある
とか、世帯主(息子)に収入があるとか、言う場合は、いままでの国民年金保険料より多く払う場合が一般的に
出てくるとおもわれる。
これは、国の政策が年金を多く給付するのは、約束事で動かしようが無いことなので、給付してから、これからの
世代に比べて多すぎる年金を医療保険料etseで国に還元してもらうことであって、老人だけで生活している低所得
者の保険料が高くなることはないので、多くの人にとって、やはり良いしくみでは、なかろうか。
「後期高齢者医療制度」がある。後期高齢者医療制度では、保険料は被保険者全員が納めることになる。
被保険者とは75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の一人一人のことだ。
保険料は(静岡県の場合)次のように決定される。
均等割額(36000円)+所得割額((総所得金額等-330,000円)×所得割率(6.84%)) =一人当たりの保険料
上記の式にあてはめると年金収入だけの被保険者については、収入額が153万以下の場合所得割はかされない。
収入が年金だけで夫婦二人の年金収入がそれぞれ153万以下だった場合は所得割は無く、均等割額の36,000円のみ
×夫婦二人分ということになるが所得が低い人は2割から7割の均等割額の軽減がありなおかつ職場の健康保険などの
被扶養者だった人の場合平成20年4月から9月は全額免除10月から翌年の3月までは9割均等割額の軽減があるため
国民健康保険料と比べてみると老人世帯の低所得(中所得)は負担が軽減されるとおもわれる。
国民健康保険(静岡市の場合)の所得割が無く夫婦二人の場合の保険料
医療分 均等割額 28,800×被保険者数=57,600円
平等割額 1世帯あたり 24,600円
介護分 均等割額 13,500×被保険者数=27,000円
合計 57,600+24,600+27,000=99,200円
となり、低所得者層で息子世帯といっしょにに暮らしていない場合は、いままで最低基準として納付していた額
10万前後とくらべ半分以下になる場合がごく一般的にでてくる。反対に年金収入が多いとか、普通に収入がある
とか、世帯主(息子)に収入があるとか、言う場合は、いままでの国民年金保険料より多く払う場合が一般的に
出てくるとおもわれる。
これは、国の政策が年金を多く給付するのは、約束事で動かしようが無いことなので、給付してから、これからの
世代に比べて多すぎる年金を医療保険料etseで国に還元してもらうことであって、老人だけで生活している低所得
者の保険料が高くなることはないので、多くの人にとって、やはり良いしくみでは、なかろうか。